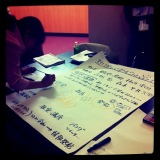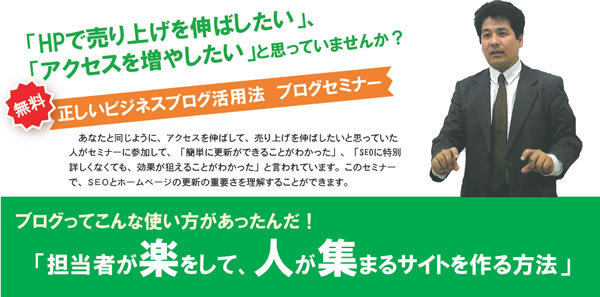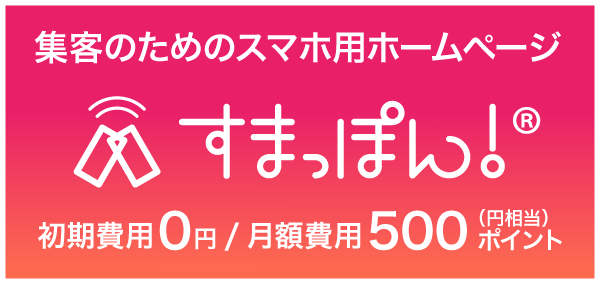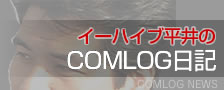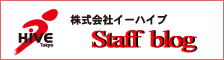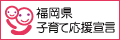その17「今頃Facebook?3 」 読み、書き、そろばん、ソーシャルメディア(仮)
at 2012/1/06 09:00:00
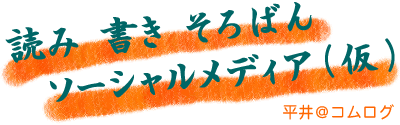
Facebookは、ツイッターやブログと違うところは、深くディスカッション・コミュニケーションが
取れるところだと思っています。
ブログにもコメント欄がありますが、会話と言うよりは単発なコメント・感想を書きこむ所ですし、
ツイッターもリツイートや返信がありますが、どうしても一対一のコミュニケーションになりがちです。
しかもツイッターは公開型なので深く会話ができませんし、流れも早く、
ゆっくりとコミュニケーションを取る場所ではなさそうです。
しかし、Facebookは、実名制なせいもありますが、ゆっくりと議論も出来ますし
複数人がコメントを残しても自分のコメント以前の議論も目で追うことができます。
私も実際に、8名での飲み会が、1時間程度で全員の時間調整をして場所も決定していたり、
セミナー講師の依頼から日程の調整まで、30分ぐらいで話が決まっていることもあります。
これは、ツイッターやブログでは難しいですし、メールではかなり調整などに時間がかかったり、
複数の人が時間を合わせるのはかなり大変だったりします。
そのが、Facebookでは、比較的簡単に出来ます。
メールとチャットの間ぐらいがいいのかもしれません。
また、グループという機能も面白い使い方できます。
一つの個人の発言からディスカッションをする場合もありますが、
一つの話題を中心に人が集まり議論・意見交換する場所が、グループです。
メーリングリストをWEBでやっていると思ったほうがわかりやすいでしょうか?
ただ、メーリングリストの場合は、誰に対する返事かわからなくなったり、
短い返事だとメーリングリストに流しにくかったりしますが、
Facebookグループの場合、「OK」とか「読みました!」なんてコメントも
発言しやすいのです。
以前、実際に面白い動きがありました。
2011年5月21日に、社会起業家のフォーラムが福岡で開かれました。
「九州ソーシャルビジネスフォーラム」です。
ここでは午前中は講演を聞いて、午後は10人程度のグループワークを行いました。
もちろん社会起業家のフォーラムですからテーマも、
「環境」「福祉」「教育」「震災復興」「地域活性化」などでした。
この中で、私がファシリテーターをさせていただいたのは、
情報化社会の中の中山間地の活かし方
【情報化ビレッジによる中山間地の活性化】
【情報化ビレッジによる中山間地の活性化】
当日の様子は、こちらから /hirai/885.html
大変盛り上がって、最後のポスターセッションまで白熱した議論が繰り広げられました。
ただ、通常こういったイベントは、その場では盛り上がるものの、
会が終わった瞬間、あとは現場の人で頑張ってねと、皆さん忘れていくものです。
次に繋がるのはほんの僅かでしょう。
しかし今回は、まだ熱が冷める前に、Facebook上にグループを作りました。
当日参加された方、人数の都合で他のグループに参加した方、
今回のイベントに参加したいけど参加できなかった方、
さらには、佐賀市の職員さん、佐賀県の職員さんなども入って頂きました。
35名ぐらいのメンバーがいらっしゃいます。
中で話している内容は、ワークセッションで当日決まった内容を現地に持っていった反応だとか、
当日来れなかった方への説明だとかが行われていました。
そんな中から、やっぱり現地を見たほうがいいんじゃないかという話が上がってきました。
それももっともだという話になり、
実際にグループを使って、日程を決めたりプログラムを決めたりしました。
また、福岡から行く人は車を乗り合わせて行くように決めたり、
現地で合流する打ち合わせなども行いました。
全てFacebookのグループ内での事です。
1週間ぐらい後には日程が決まり、2週間後のには現地に大分や四国から
15名もの人が集まってきました。
今までであれば考えられない動きです。この15名は、フォーラム前は殆ど
顔も名前をも知らない人同士だったのですから。
その後も、現地から「地域の特産品を作ってます!」や、
「こんなパッケージにしてみましたが、どうですか?」
などの情報交換が行われ、最終的には佐賀市富士町からの特産品「ふじから便」として、
「干しタケノコのキンピラ」「こんにゃくのキンピラ」などのお惣菜が登場した様子もよくわかりました。
この商品が8月には博多大丸に出品され、その時はメンバーがこぞって買いに行き、
写真をパチリ、それに感想を付けてツイッターやFacebook、ブログを更新!
そう、この関係者達は、立派な佐賀富士町の広報委員となっていたのです。
グループでは、同じテーマを持つ人が集まって情報交換しているので、
こんなことも起きるんです。
ただ、それから半年。現在このグループがどうなっているかというと、
実在するにはしますが、もう盛り上がっていないのです。
私は、グループには賞味期限があると思っています。
あるテーマで集まって盛り上がるのは2~3ヶ月。
メーリングリストと同じ性格だと思います。
盛り上がって作ったメーリングリストは、最初は活発に意見交換が行えますが、
マンネリ化しだすと殆どの人は、目も通さなくなります。
メールが届いてもそのまま特定のメールフォルダへ直行
必然的に、告知に使いたい人の情報が流れていて、一方方向なツールに変わっていき、
かろうじて閲覧していた人も、見なくなる。ということが起きてきます。
グループも全く同じことが起こっているので、ある程度成熟したら、
テーマを変えたりメンバーを変えて、グループを再構築するのがいいのではと思っています。
もちろん今までのグループはアーカイブとして残しておいてもいいです。
また、人数が多すぎるグループも同様なことが起きるので、テーマを分けたり分科会にしても
いいのではないでしょうか?
つまりあくまでもツールなので、どう使うかは皆さん次第です!
シリーズ「読み、書き、そろばん、ソーシャルメディア(仮)」
===============
コミュニケーションブログ COMLOG https://www.com
中小企業向け コムログクラウド https://cloud.c
福岡ショップ情報局 http://fukuoka.
===============
 ツイッターアカウントは、@comlog
ツイッターアカウントは、@comlog - コメント (0)
- トラックバック (0)
- トラックバックURL : http://www.i-hive.co.jp/tb.cgi/1300